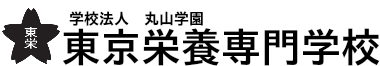2024年12月5日、日本酒や焼酎、泡盛といった「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました!
日本の酒造りの伝統の技が世界に認められてうれしい限りです。
さて日本酒のラベルの原材料を見ると、米と米こうじとしか書いてありません。
ここからどうしてアルコールが発生するのでしょうか?
一般的にアルコールは酵母が原料の糖分をえさにして発酵する際にアルコールと炭酸ガスを発生させます。
日本の伝統的酒造りのアルコールもこの原理を利用して生成されますが、その時に「こうじ」が重要な役割をします。
原料であるお米に含まれるデンプンを米こうじが糖分に変えて(糖化)、さらにその糖分を酵母のはたらきによってアルコールと炭酸ガスに変えるという2つの作用を同時に進める「並行複発酵」という手法がとられていて、これは世界でもとても珍しい手法です。
「並行複発酵」は発酵の進行を適度に保つのが難しく、杜氏や蔵人らは経験を重ねながら、500年以上にわたって高度な技術を磨いてきました。
また泡盛は約600年の歴史を誇る日本最古の蒸留酒ですが、製造過程で「黒こうじ菌」を使うのが特徴です。この「黒こうじ菌」は泡盛の製造過程で大量のクエン酸を生成して、雑菌による腐敗を抑えることができるので、温暖で湿潤な沖縄の気候にとても適しているそうです。
このように「伝統的酒造り」は日本の気候や風土とともに発展し受け継がれています。
江戸時代の頃より「良いお酒ができますように」という願いを込めてかけられる「杉玉」
その願いは昔も今もずっと変わらないことでしょう。

♯東京栄養専門学校 ♯栄養士 ♯専門学校 ♯西新宿 ♯新宿 ♯伝統的酒造り ♯無形文化遺産 ♯並行複発酵