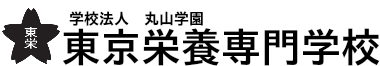新年あけましておめでとうございます。
冬季休業期間を終えて、今日から学校も始まりました!
本年もよろしくお願いいたします。
今年最初のブログは七草がゆの話題から…
1月7日は七草がゆを食べる日として有名です。
この日は人日(じんじつ)の節句または七草の節句とも呼ばれます。
調べてみると、「人日」という言葉は古代中国に由来していました。
前漢の時代、1月1日~7日までの各日に動物をあてはめて占う風習があって、
1日は鶏、2日は狗、3日は羊など…、それぞれの日にはそれぞれの動物を大切にして、
殺生を行わないようにしていたそうです。
そして7日は「人の日」(人日)
この日は人間を大切にする日として、「人日の日」の節句に定めました。
時はさらに流れて唐の時代、「人日の日」に7種類の野菜を入れた汁ものを食べたとされます。
この中国由来の風習が奈良時代に日本に伝わると、元々、日本にあった風習と結びつき「七草粥」へと変化していき、そして江戸時代に入ると、七草の節句は五節句のひとつとして人々に定着しました。
春の七草は、「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の7種類の野草のこと。これらの七草をお粥に入れたものを1月7日に食べて、その年の無病息災を祈ります。
栄養面では、七草粥は薬膳としても年末年始に食べすぎた胃腸をいたわる効果や、各種ビタミンやミネラルの成分が風邪予防としても効果的かと思います。
お正月最後の日に七草粥を食べてみませんか?

♯東京栄養専門学校 ♯栄養士 ♯専門学校 ♯西新宿 ♯新宿 ♯七草がゆ ♯七草粥 ♯人日の節句 ♯七草の節句 ♯春の七草